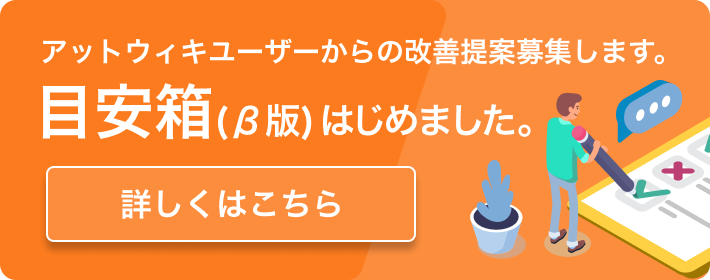誤解と無自覚の連鎖反応
「あ~、いたいた! レントさ~ん!」
「――っ!」
不意に背後から掛けられた声に、青年は弾かれたようにびくりと身を竦めた。
二十歳過ぎに見える長身の青年。綿雪のような白髪に、暁闇を思わせる紫紺の瞳。白皙の上の面立ちは端整にして怜悧。
片手に杖、頭にはとんがり帽子、青いマントとローブを身につけたその姿は、一目で魔術師だと知れる。
青年は杖を持たぬ腕に、口までぎっしり中身の入った紙袋を抱えていた。長身に見合って長い腕のため、何とか片腕で
事足りているが、かなりギリギリなバランスである。
何かの拍子で崩れそうな均衡は――案の定、青年が慌てて振り返ったことで崩れた。紙袋の口から中身が零れ、
ごろごろと暗い裏路地に転がる。
「あ――」
「ああぁぁ~~~、リンゴが~~~!」
青年が自身の失態へ漏らした呻きに被り、先程の声の主が悲鳴を上げた。
十七、八歳ほどの小柄な少女。肩ほどまでの亜麻色の髪に、感情がそのまま映る大きな緑の瞳。美麗ではないが十分に
愛らしい面立ち。そんな見る者の保護欲を誘う可憐な容姿とは裏腹に、身に纏っているのは身体の要所を守る軽鎧。
その上、腰に大剣を帯びている。
どうにも容姿と服装がちぐはぐなその少女は、道に散らばったリンゴを拾おうとしてか、あたふたと中腰に。そのまま
足を前に踏み出して――マント代わりに巻いていた自身のマフラーを踏みつけて、前につんのめった。
「うきゃっ!」
「ノエル!?」
いっそ感心するほどキレイに転んだ少女へ、青年は焦った様子で身を屈め、
「あっ――」
「ああぁぁぁ~~~! リンゴ~~~!」
紙袋の中に辛うじて残っていた中身まで、道にぶちまけてしまうのだった。
「――っ!」
不意に背後から掛けられた声に、青年は弾かれたようにびくりと身を竦めた。
二十歳過ぎに見える長身の青年。綿雪のような白髪に、暁闇を思わせる紫紺の瞳。白皙の上の面立ちは端整にして怜悧。
片手に杖、頭にはとんがり帽子、青いマントとローブを身につけたその姿は、一目で魔術師だと知れる。
青年は杖を持たぬ腕に、口までぎっしり中身の入った紙袋を抱えていた。長身に見合って長い腕のため、何とか片腕で
事足りているが、かなりギリギリなバランスである。
何かの拍子で崩れそうな均衡は――案の定、青年が慌てて振り返ったことで崩れた。紙袋の口から中身が零れ、
ごろごろと暗い裏路地に転がる。
「あ――」
「ああぁぁ~~~、リンゴが~~~!」
青年が自身の失態へ漏らした呻きに被り、先程の声の主が悲鳴を上げた。
十七、八歳ほどの小柄な少女。肩ほどまでの亜麻色の髪に、感情がそのまま映る大きな緑の瞳。美麗ではないが十分に
愛らしい面立ち。そんな見る者の保護欲を誘う可憐な容姿とは裏腹に、身に纏っているのは身体の要所を守る軽鎧。
その上、腰に大剣を帯びている。
どうにも容姿と服装がちぐはぐなその少女は、道に散らばったリンゴを拾おうとしてか、あたふたと中腰に。そのまま
足を前に踏み出して――マント代わりに巻いていた自身のマフラーを踏みつけて、前につんのめった。
「うきゃっ!」
「ノエル!?」
いっそ感心するほどキレイに転んだ少女へ、青年は焦った様子で身を屈め、
「あっ――」
「ああぁぁぁ~~~! リンゴ~~~!」
紙袋の中に辛うじて残っていた中身まで、道にぶちまけてしまうのだった。
◇ ◆ ◇
少女はノエル=グリーンフィールド。赤子の頃にヴァンスターの貴族・グリーンフィールド家に拾われ、愛情深く育てられた少女。
青年はレント=セプター。ノエルの実父である“大首領”が興した『地域密着型の悪の組織』、ネオ・ダイナストカバルにより
生み出された人造生命。
ノエルは二年前、十六の誕生日に自身の出生を追って旅立った。その旅路で成した業績により、いまやこのエリンディル
大陸全土にその名を知られている、ギルド“フォア・ローゼス”のマスターである。
世界を救った“薔薇の巫女”。人の口には生きる伝説として語られる彼女だが、お人好しで、あわてんぼうで、すぐ人に
騙されてしまう、ちょっと危なっかしい少女である。
レントは起動から二年にも満たぬ、人にすれば赤子の実年齢。しかし、その知性と知識は並みの成人など軽く凌駕し、
ギルドの軍師的役割を担うほどだ。
そんなレントの性格は冷静沈着――というより、“前任者”の不慮の事態により起動直後に実戦投入された弊害から、
やや感情の機微に疎い。しかし、それ故に、焦り等からミスするような事態は殆どない――のだが。
「申し訳ありません……」
慌てて振り返った拍子に零し、その上屈んでぶちまけてしまったリンゴを拾い集めながら、レントは弱い声でノエルに
告げた。淡々とした中にも、沈んだ調子が滲んでいる。
「ああぁぁ~~~っ、そんなっ……気にしないで下さいっ。
元はといえば、あたしがいきなり後ろから声をかけたのがいけなかったんですからっ」
一緒にリンゴを拾い集めながら、ぶんぶんと首を横に振るノエル。
だが、レントは俯いたまま、ノエルの言葉を否定する。
「いえ、わたしのミスです。もっと荷のバランスを気遣って振り返ればよかったのですから」
「それは、あたしがいきなり声をかけちゃったせいで~……」
「いえ、ノエルは悪くありません」
ノエルの言葉を遮って、レントは言い切る。その声には、これ以上フォローされることを拒む色。ここでまた、ノエルが
フォローしたとしても、延々ループするだけだろう。
しかしノエルからすれば、これは自分が原因だ。それでレントを沈んだままにしておくのは耐えられない。
「え、えとえとえと! で、でもすごいですねリンゴこんなにいっぱい! どうしたんですか!?」
フォローできないなら、せめて話題を変えようと、ノエルは思いついたことを咄嗟に口にした。
レントは、多少沈んだ様子のままながらも、律儀にノエルの質問に答えた。
「支部へ挨拶に行ったら、『近所の農家の方にたくさん貰ったから、そのおすそ分けだ』と。
ここの人員はそう多くないので、処理しきれないようで」
レントの言う『支部』とは、説明するまでもなく、ネオ・ダイナストカバルの支部のことである。ギルド“フォア・ローゼス”が
とある事情でしばらくこの町に滞在することとなったので、彼はそこへ挨拶に行っていたのだ。
「なるほど~。これだけいっぱいだと、食べきるの大変ですもんね~。……でもそれなら任せてください!
あたし、リンゴ大好きですから! いっぱい食べますよ~!」
ぐっと拳を握って宣言するノエルに、レントは一瞬目を見開く。
次いで、微かにその表情を緩めると、淡々とした声音に、仄かに暖かな色を宿して、
「それは良かった。ですが、そのままで食べるのにも限度があるでしょうから、何か菓子にでもわたしが調理しましょう。
ノエルは何がお好きですか?」
その申し出もさることながら、何より彼の表情から沈んだ色が消えたことが嬉しくて、ノエルは満面の笑みで答えた。
「レントさんの作ったものなら何でも! 絶対おいしいですから!」
次の瞬間。
「あああぁぁぁぁ~~~!? どどどどうしたんですかレントさんっ!?」
「……も、申し訳ありません……手が滑りました……」
レントがせっかく拾い集めたリンゴを再びぶちまけ、気まずそうに慌てて掻き集めるのだった。
青年はレント=セプター。ノエルの実父である“大首領”が興した『地域密着型の悪の組織』、ネオ・ダイナストカバルにより
生み出された人造生命。
ノエルは二年前、十六の誕生日に自身の出生を追って旅立った。その旅路で成した業績により、いまやこのエリンディル
大陸全土にその名を知られている、ギルド“フォア・ローゼス”のマスターである。
世界を救った“薔薇の巫女”。人の口には生きる伝説として語られる彼女だが、お人好しで、あわてんぼうで、すぐ人に
騙されてしまう、ちょっと危なっかしい少女である。
レントは起動から二年にも満たぬ、人にすれば赤子の実年齢。しかし、その知性と知識は並みの成人など軽く凌駕し、
ギルドの軍師的役割を担うほどだ。
そんなレントの性格は冷静沈着――というより、“前任者”の不慮の事態により起動直後に実戦投入された弊害から、
やや感情の機微に疎い。しかし、それ故に、焦り等からミスするような事態は殆どない――のだが。
「申し訳ありません……」
慌てて振り返った拍子に零し、その上屈んでぶちまけてしまったリンゴを拾い集めながら、レントは弱い声でノエルに
告げた。淡々とした中にも、沈んだ調子が滲んでいる。
「ああぁぁ~~~っ、そんなっ……気にしないで下さいっ。
元はといえば、あたしがいきなり後ろから声をかけたのがいけなかったんですからっ」
一緒にリンゴを拾い集めながら、ぶんぶんと首を横に振るノエル。
だが、レントは俯いたまま、ノエルの言葉を否定する。
「いえ、わたしのミスです。もっと荷のバランスを気遣って振り返ればよかったのですから」
「それは、あたしがいきなり声をかけちゃったせいで~……」
「いえ、ノエルは悪くありません」
ノエルの言葉を遮って、レントは言い切る。その声には、これ以上フォローされることを拒む色。ここでまた、ノエルが
フォローしたとしても、延々ループするだけだろう。
しかしノエルからすれば、これは自分が原因だ。それでレントを沈んだままにしておくのは耐えられない。
「え、えとえとえと! で、でもすごいですねリンゴこんなにいっぱい! どうしたんですか!?」
フォローできないなら、せめて話題を変えようと、ノエルは思いついたことを咄嗟に口にした。
レントは、多少沈んだ様子のままながらも、律儀にノエルの質問に答えた。
「支部へ挨拶に行ったら、『近所の農家の方にたくさん貰ったから、そのおすそ分けだ』と。
ここの人員はそう多くないので、処理しきれないようで」
レントの言う『支部』とは、説明するまでもなく、ネオ・ダイナストカバルの支部のことである。ギルド“フォア・ローゼス”が
とある事情でしばらくこの町に滞在することとなったので、彼はそこへ挨拶に行っていたのだ。
「なるほど~。これだけいっぱいだと、食べきるの大変ですもんね~。……でもそれなら任せてください!
あたし、リンゴ大好きですから! いっぱい食べますよ~!」
ぐっと拳を握って宣言するノエルに、レントは一瞬目を見開く。
次いで、微かにその表情を緩めると、淡々とした声音に、仄かに暖かな色を宿して、
「それは良かった。ですが、そのままで食べるのにも限度があるでしょうから、何か菓子にでもわたしが調理しましょう。
ノエルは何がお好きですか?」
その申し出もさることながら、何より彼の表情から沈んだ色が消えたことが嬉しくて、ノエルは満面の笑みで答えた。
「レントさんの作ったものなら何でも! 絶対おいしいですから!」
次の瞬間。
「あああぁぁぁぁ~~~!? どどどどうしたんですかレントさんっ!?」
「……も、申し訳ありません……手が滑りました……」
レントがせっかく拾い集めたリンゴを再びぶちまけ、気まずそうに慌てて掻き集めるのだった。
◇ ◆ ◇
「絶対変ですよぅ~……」
こてん、と食堂のテーブルに顎を載せて、ノエルは絶対可憐な呻き声を上げた。
「変? 何がだ?」
その呻きを聞き留めて、同じテーブルについていた女性が問いを投げる。
二十歳前後の若い娘。緩やかに波打つ腰ほどまでの金髪、深い青玉石(サファイア)の眼差し。その面立ちは、思わず
目を奪われてしまうほどに麗しい。すらりとした肢体に纏う赤いドレス、揃いの赤い帽子が髪に映えていた。
彼女の名はエイプリル=スプリングス。容姿に似合わぬ渋い言動が特徴のシーフ、“フォア・ローゼス”の危機回避担当だ。
ダンジョンでの罠の発見・解除は勿論、すぐ詐欺に引っかかるマスターへのフォローも彼女の役割である。
宿の食堂でくつろぐからと武装を解いたノエルとは違い、彼女は腰に武器を下げたまま。使い込まれた二丁の魔導銃は、
彼女が熟練のガンスリンガーだと告げていた。
「レントさんですっ。なんだか変なんですよぅっ」
「……レントが?」
ノエルの返答に首を傾げたのは、テーブルに着いた最後の一人、唯一の男性だった。
エイプリルとそう変わらない年頃の青年。癖のない肩程までの金髪に、澄んだ青の瞳。柔和で中性的な面立ちだが、
ラフな普段着から垣間見える体躯は、細身ながらも鍛錬を積んだ頑健なもの。
クリス=ファーデナント。戦闘時には、防護魔法と鎧を着込んだ自らの体躯でギルドの盾となる神官騎士だ。
しかし、今の彼は装備を身につけてはいない。彼の鉄壁の守りたる装備達は、頑健さに比例する重量を誇るのだ。
くつろぐ時には正直邪魔である。
「あいつは元々変でしょう? 仏頂面だし、時々突拍子もない変なこと言うし」
『手乗りババア』とか、などとクリスは言って、レントがいる厨房の方に半眼を向ける。
夕餉の後、レントは宿の主に頼んで厨房を借り、夕方に貰ってきたリンゴを菓子に調理している最中だ。距離があるので、
普通に話しても声は届かない。
「ひどっ、ひどいですよクリスさんっ! 真剣に話してるのにっ」
「す、すいません、つい……」
頬を膨らませて抗議するノエルに、クリスは苦笑して詫びる。
レントの属するネオ・ダイナストカバルは、『対神殿』をスローガンに掲げる組織だ。
その実、テロ行為をするわけでもなく、ボランティア活動やらに精を出しつつ神殿の悪口をせこせこ広めるという、実に
平和な抗議活動。組織の人員も、好ましい人々であることはクリスも目の当たりにしている。
それでも、神官であるクリスとしては、ことあるごとに神殿をあげつらうレントに対して、つい突っかかるような物言いに
なってしまうのである。これは不仲というより、喧嘩するほど何とやら、の類なのだが。
「で、レントがどう変なんだ?」
クリスに助け舟を出したわけでもないだろうが、エイプリルが話題を戻す。
「えぇ~と……うまくいえないけど、ともかく変なんです。らしくないっていうか……」
首を傾げつつ、ノエルは答える。そうして、夕方、支部まで彼を迎えに行って、合流してからの彼の行動を語った。
「あたしが後ろから声をかけたら、妙に慌てた様子で振り返ってリンゴ落っことしちゃうし。
あたしがリンゴ拾おうとして転んじゃったら、助け起こそうとしてくれたんですけど、その拍子にまたリンゴ落としちゃうし……」
「……レントがノエル絡みで必死なのは、いつものことでしょう?」
軽く首を傾けて、クリスは疑問を差し挟む。
レントは起動されてすぐに、絶対の忠誠を誓う大首領より、息女・ノエルの護衛を命じられた。その命令は現在でも、
彼の中で第一位優先事項である。彼にとって、ノエルは何を投げ打っても守るべき対象なのだ。
そんな彼ならば、ノエルの声に過剰に反応するのも、転んだノエルを慌てて助けようとするのも当然のように思えるが――
「いや、確かにノエルの言う通り、レントらしくない。
ノエル絡みだったらなおのこと、あいつは間違いのない手順で行動するだろ」
エイプリルが、クリスの言葉に答えて言う。
「慌てて振り返ってリンゴを落としたら、ノエルがそのリンゴに躓いて転ぶかもしれない。
転んだノエルを起こすために慌てて屈んだら、抱えたリンゴがノエルの上に落ちるかもしれない。
――それくらいの判断は、いつものあいつなら咄嗟にできるはずだぞ」
「た、確かに……」
レントの判断速度はギルド随一だ。ノエル絡みならなおのこと、その能力はフルに発揮される。エイプリルの言葉に、
クリスもやや訝しげな顔色になった。
表情を曇らせたノエルが、更に告げる。
「それだけじゃないんですよっ! リンゴを拾ってる最中にいきなりリンゴ全部落っことしちゃったんですっ。
その後も、何だか動きがギクシャクしてて……宿に戻る頃には治ってたんですけど……」
「それは……」
聞いたクリスの顔色も硬いものになる。恐いような声音で、低く呻いた。
「あいつ……まさか、どっか悪いのか……!?」
「――待て、どこ行く気だ?」
言うなり立ちあがったクリスの腕を掴み、エイプリルが問う。
「決まってる! あいつに直接訊いてくるんだ!」
クリスは語気荒く即答する。
人造生命であるレントが、人間と同じように病に罹るかはわからないが、もしかしたら、彼は身体に何らかの変調を
きたしているのかも知れない。そう思ったら、いてもたってもいられなかったのだ。
レントの“前任者”――彼の“兄”は、自分のせいで命を落とした。事実はどうあれ、クリスにはその思いがある。
その思いから、ただいたずらに自身を責める気は毛頭ないが、再び仲間に――それも、彼の“弟”に何かあれば、
それこそ自分を許せなくなる。
「落ち着け! 訊いた程度で答えるなら、あいつは自分から話してるだろうが」
「それは……」
エイプリルの一喝に、クリスは低く呻いて項垂れる。
「本当に深刻な事態なら、レントは自分から言うだろう。あいつはこのギルドの軍師役だ。あいつ自身、それを自覚してる。
戦闘中に自分に何かあれば、自分だけでなくノエルや俺たちにも危険が及ぶとわかってるはずだ。
その状況であいつが自身の不調を黙秘するとは思えない、黙っている以上は大したことじゃないんだろう」
エイプリルの言葉に、クリスはしぶしぶ納得したように席に直った。
「じゃあ……あいつの様子が変なのは?」
「そうですよ~、具合が悪いんじゃなかったら、どうして様子がおかしいんですか?」
クリスとノエル、二人がかりで詰め寄られ、エイプリルは何故か、どこか面白がるような笑みを浮かべて、
「そうだな……複雑なお年頃、ってやつじゃないのか?」
は? と首を傾げる二人に、エイプリルは意味深な笑みを浮かべて、喉の奥で笑った。
「おい? なに笑ってるんだお前は!?」
「そ、そうですよぅ~っ、なにがおかしいんですか~!?」
「いや、悪い……けど、お前らもそう深刻になるなよ」
眉を吊り上げて怒鳴るクリスに、眉を垂らして情けない声を漏らすノエル。そんな二人の様子に、エイプリルはますます
笑みを深くする。
喉から零れる笑いを殺し、頬杖をつきながら二人に告げた。
「レントは、ナリはああでも実際にはガキなんだ。ガキなら、精神的に不安定になることもあるだろう」
「精神的に……って……ああ! そういうことか!」
「えぇ? なにが……なにがですかっ!?」
ぽんっ、と手を打って納得の表情を浮かべるクリスを、疑問顔のままのノエルが見上げる。
「簡単ですよ。子供が不安になるのは、母親と離れてる時。
もちろん、人造生命であるレントに母親はいませんが、母親代わりはいるでしょう?」
「あ! なるほど~! アルテアさんがいないから、レントさん寂しいんですね!」
確信に満ちた口調で告げるクリスに、ノエルも納得の表情を浮かべる。
その横で、エイプリルが珍しくテーブルに突っ伏しかけたりしていたのだが、残念ながら二人ともそれに気付けなかった。
アルテア。ネオ・ダイナストカバルの幹部にして、“フォア・ローゼス”の旅に同行するエルダナーンの少女である。
外見は――というか、言動も――十歳前後だが、長寿であるエルダナーンゆえ、実年齢はわからない。明朗快活、
何事にも直球で、感情の流れが素直な彼女は、情緒面で未熟なレントの教育係として、彼に同行している。
いわばレントの母親代わりである彼女は、二ヶ月前から“フォア・ローゼス”と分かれ、ネオ・ダイナストカバルの本部に
戻っていた。
何でも、レントの生みの親であるドクトル・セプターに、新たな研究開発の手伝いとして呼び戻されたのだという。研究の
内容は聞かされていないのでわからないが、もしかしたら、近いうちにレントの“兄弟”が増えるのかもしれない。
ともあれ、その手伝いを一段落させたアルテアが、明日にでも“フォア・ローゼス”と合流すべく本部を発つと、今朝方
連絡があったのだ。
神殿の転送装置や転送石を使えば一瞬で済むところを、対神殿組織の幹部は、自分の足で合流するつもりらしい。
本部からこの町まで早くて十日ほど。天候などによってはその倍近くかかるが、その間、ノエル達はこの町に逗留し、
アルテアを待つことになったのである。
「しっかし……あいつでも母親と離れたら心細くなるような繊細さがあったんだなぁ……」
一人で懸命に留守番していた子供が、これから帰るという母からの報せに、寂しさを堰切らせたのだろうか。
レントの心情をそんな風に推察して、クリスはしみじみと呟いた。
「あ! あたし、レントさんのお手伝いしてきます! 一人じゃ寂しいかもしれないし!」
「え? おい、それは――」
一方、ノエルはなにやら母性本能をくすぐられたのか、勢いよく立ち上がって厨房へと向かう。エイプリルの制止の声も
届いてない様子だった。
溜息に混じって、エイプリルは呟く。
「……まともな菓子が食えるといいがな……」
「おい、エイプリル、それはノエルに失礼だぞ」
クリスの言葉に、そういう意味じゃない、と返しかけたエイプリルの呆れ声は、厨房から響いた破砕音と、ノエルの悲鳴に
掻き消されたのだった。
こてん、と食堂のテーブルに顎を載せて、ノエルは絶対可憐な呻き声を上げた。
「変? 何がだ?」
その呻きを聞き留めて、同じテーブルについていた女性が問いを投げる。
二十歳前後の若い娘。緩やかに波打つ腰ほどまでの金髪、深い青玉石(サファイア)の眼差し。その面立ちは、思わず
目を奪われてしまうほどに麗しい。すらりとした肢体に纏う赤いドレス、揃いの赤い帽子が髪に映えていた。
彼女の名はエイプリル=スプリングス。容姿に似合わぬ渋い言動が特徴のシーフ、“フォア・ローゼス”の危機回避担当だ。
ダンジョンでの罠の発見・解除は勿論、すぐ詐欺に引っかかるマスターへのフォローも彼女の役割である。
宿の食堂でくつろぐからと武装を解いたノエルとは違い、彼女は腰に武器を下げたまま。使い込まれた二丁の魔導銃は、
彼女が熟練のガンスリンガーだと告げていた。
「レントさんですっ。なんだか変なんですよぅっ」
「……レントが?」
ノエルの返答に首を傾げたのは、テーブルに着いた最後の一人、唯一の男性だった。
エイプリルとそう変わらない年頃の青年。癖のない肩程までの金髪に、澄んだ青の瞳。柔和で中性的な面立ちだが、
ラフな普段着から垣間見える体躯は、細身ながらも鍛錬を積んだ頑健なもの。
クリス=ファーデナント。戦闘時には、防護魔法と鎧を着込んだ自らの体躯でギルドの盾となる神官騎士だ。
しかし、今の彼は装備を身につけてはいない。彼の鉄壁の守りたる装備達は、頑健さに比例する重量を誇るのだ。
くつろぐ時には正直邪魔である。
「あいつは元々変でしょう? 仏頂面だし、時々突拍子もない変なこと言うし」
『手乗りババア』とか、などとクリスは言って、レントがいる厨房の方に半眼を向ける。
夕餉の後、レントは宿の主に頼んで厨房を借り、夕方に貰ってきたリンゴを菓子に調理している最中だ。距離があるので、
普通に話しても声は届かない。
「ひどっ、ひどいですよクリスさんっ! 真剣に話してるのにっ」
「す、すいません、つい……」
頬を膨らませて抗議するノエルに、クリスは苦笑して詫びる。
レントの属するネオ・ダイナストカバルは、『対神殿』をスローガンに掲げる組織だ。
その実、テロ行為をするわけでもなく、ボランティア活動やらに精を出しつつ神殿の悪口をせこせこ広めるという、実に
平和な抗議活動。組織の人員も、好ましい人々であることはクリスも目の当たりにしている。
それでも、神官であるクリスとしては、ことあるごとに神殿をあげつらうレントに対して、つい突っかかるような物言いに
なってしまうのである。これは不仲というより、喧嘩するほど何とやら、の類なのだが。
「で、レントがどう変なんだ?」
クリスに助け舟を出したわけでもないだろうが、エイプリルが話題を戻す。
「えぇ~と……うまくいえないけど、ともかく変なんです。らしくないっていうか……」
首を傾げつつ、ノエルは答える。そうして、夕方、支部まで彼を迎えに行って、合流してからの彼の行動を語った。
「あたしが後ろから声をかけたら、妙に慌てた様子で振り返ってリンゴ落っことしちゃうし。
あたしがリンゴ拾おうとして転んじゃったら、助け起こそうとしてくれたんですけど、その拍子にまたリンゴ落としちゃうし……」
「……レントがノエル絡みで必死なのは、いつものことでしょう?」
軽く首を傾けて、クリスは疑問を差し挟む。
レントは起動されてすぐに、絶対の忠誠を誓う大首領より、息女・ノエルの護衛を命じられた。その命令は現在でも、
彼の中で第一位優先事項である。彼にとって、ノエルは何を投げ打っても守るべき対象なのだ。
そんな彼ならば、ノエルの声に過剰に反応するのも、転んだノエルを慌てて助けようとするのも当然のように思えるが――
「いや、確かにノエルの言う通り、レントらしくない。
ノエル絡みだったらなおのこと、あいつは間違いのない手順で行動するだろ」
エイプリルが、クリスの言葉に答えて言う。
「慌てて振り返ってリンゴを落としたら、ノエルがそのリンゴに躓いて転ぶかもしれない。
転んだノエルを起こすために慌てて屈んだら、抱えたリンゴがノエルの上に落ちるかもしれない。
――それくらいの判断は、いつものあいつなら咄嗟にできるはずだぞ」
「た、確かに……」
レントの判断速度はギルド随一だ。ノエル絡みならなおのこと、その能力はフルに発揮される。エイプリルの言葉に、
クリスもやや訝しげな顔色になった。
表情を曇らせたノエルが、更に告げる。
「それだけじゃないんですよっ! リンゴを拾ってる最中にいきなりリンゴ全部落っことしちゃったんですっ。
その後も、何だか動きがギクシャクしてて……宿に戻る頃には治ってたんですけど……」
「それは……」
聞いたクリスの顔色も硬いものになる。恐いような声音で、低く呻いた。
「あいつ……まさか、どっか悪いのか……!?」
「――待て、どこ行く気だ?」
言うなり立ちあがったクリスの腕を掴み、エイプリルが問う。
「決まってる! あいつに直接訊いてくるんだ!」
クリスは語気荒く即答する。
人造生命であるレントが、人間と同じように病に罹るかはわからないが、もしかしたら、彼は身体に何らかの変調を
きたしているのかも知れない。そう思ったら、いてもたってもいられなかったのだ。
レントの“前任者”――彼の“兄”は、自分のせいで命を落とした。事実はどうあれ、クリスにはその思いがある。
その思いから、ただいたずらに自身を責める気は毛頭ないが、再び仲間に――それも、彼の“弟”に何かあれば、
それこそ自分を許せなくなる。
「落ち着け! 訊いた程度で答えるなら、あいつは自分から話してるだろうが」
「それは……」
エイプリルの一喝に、クリスは低く呻いて項垂れる。
「本当に深刻な事態なら、レントは自分から言うだろう。あいつはこのギルドの軍師役だ。あいつ自身、それを自覚してる。
戦闘中に自分に何かあれば、自分だけでなくノエルや俺たちにも危険が及ぶとわかってるはずだ。
その状況であいつが自身の不調を黙秘するとは思えない、黙っている以上は大したことじゃないんだろう」
エイプリルの言葉に、クリスはしぶしぶ納得したように席に直った。
「じゃあ……あいつの様子が変なのは?」
「そうですよ~、具合が悪いんじゃなかったら、どうして様子がおかしいんですか?」
クリスとノエル、二人がかりで詰め寄られ、エイプリルは何故か、どこか面白がるような笑みを浮かべて、
「そうだな……複雑なお年頃、ってやつじゃないのか?」
は? と首を傾げる二人に、エイプリルは意味深な笑みを浮かべて、喉の奥で笑った。
「おい? なに笑ってるんだお前は!?」
「そ、そうですよぅ~っ、なにがおかしいんですか~!?」
「いや、悪い……けど、お前らもそう深刻になるなよ」
眉を吊り上げて怒鳴るクリスに、眉を垂らして情けない声を漏らすノエル。そんな二人の様子に、エイプリルはますます
笑みを深くする。
喉から零れる笑いを殺し、頬杖をつきながら二人に告げた。
「レントは、ナリはああでも実際にはガキなんだ。ガキなら、精神的に不安定になることもあるだろう」
「精神的に……って……ああ! そういうことか!」
「えぇ? なにが……なにがですかっ!?」
ぽんっ、と手を打って納得の表情を浮かべるクリスを、疑問顔のままのノエルが見上げる。
「簡単ですよ。子供が不安になるのは、母親と離れてる時。
もちろん、人造生命であるレントに母親はいませんが、母親代わりはいるでしょう?」
「あ! なるほど~! アルテアさんがいないから、レントさん寂しいんですね!」
確信に満ちた口調で告げるクリスに、ノエルも納得の表情を浮かべる。
その横で、エイプリルが珍しくテーブルに突っ伏しかけたりしていたのだが、残念ながら二人ともそれに気付けなかった。
アルテア。ネオ・ダイナストカバルの幹部にして、“フォア・ローゼス”の旅に同行するエルダナーンの少女である。
外見は――というか、言動も――十歳前後だが、長寿であるエルダナーンゆえ、実年齢はわからない。明朗快活、
何事にも直球で、感情の流れが素直な彼女は、情緒面で未熟なレントの教育係として、彼に同行している。
いわばレントの母親代わりである彼女は、二ヶ月前から“フォア・ローゼス”と分かれ、ネオ・ダイナストカバルの本部に
戻っていた。
何でも、レントの生みの親であるドクトル・セプターに、新たな研究開発の手伝いとして呼び戻されたのだという。研究の
内容は聞かされていないのでわからないが、もしかしたら、近いうちにレントの“兄弟”が増えるのかもしれない。
ともあれ、その手伝いを一段落させたアルテアが、明日にでも“フォア・ローゼス”と合流すべく本部を発つと、今朝方
連絡があったのだ。
神殿の転送装置や転送石を使えば一瞬で済むところを、対神殿組織の幹部は、自分の足で合流するつもりらしい。
本部からこの町まで早くて十日ほど。天候などによってはその倍近くかかるが、その間、ノエル達はこの町に逗留し、
アルテアを待つことになったのである。
「しっかし……あいつでも母親と離れたら心細くなるような繊細さがあったんだなぁ……」
一人で懸命に留守番していた子供が、これから帰るという母からの報せに、寂しさを堰切らせたのだろうか。
レントの心情をそんな風に推察して、クリスはしみじみと呟いた。
「あ! あたし、レントさんのお手伝いしてきます! 一人じゃ寂しいかもしれないし!」
「え? おい、それは――」
一方、ノエルはなにやら母性本能をくすぐられたのか、勢いよく立ち上がって厨房へと向かう。エイプリルの制止の声も
届いてない様子だった。
溜息に混じって、エイプリルは呟く。
「……まともな菓子が食えるといいがな……」
「おい、エイプリル、それはノエルに失礼だぞ」
クリスの言葉に、そういう意味じゃない、と返しかけたエイプリルの呆れ声は、厨房から響いた破砕音と、ノエルの悲鳴に
掻き消されたのだった。
◇ ◆ ◇
またやってしまった、とレントは深く嘆息し、ベッドに横たわった。
二つ取った二人部屋のうち、男二人に割り振られた部屋だ。クリスは鍛錬の一環として外へ走りこみに行っている。
一人で、誰にも気兼ねしないで済むこの状況が、今のレントにはありがたかった。
昼間はノエルの前でリンゴをぶちまけ、さっきはノエルが厨房に来た途端、何故かひどく動揺し、皿を落として割ってしまった。
幸い、自身にもノエルにも怪我はなかったし、割ってしまった皿のことも、気の好い宿の主人は笑って許してくれた。
無事だった菓子も良い出来で、甘い物好きのノエルや健啖家のエイプリルにはもちろん、自分に対して憎まれ口の多いクリス、
そして、皿の侘び代わりに振舞った店主からも、絶賛された。
だが、それでも、この気鬱は晴れない。
(このまま、この症状が続くのは拙い……)
その思いが、胸にずっと渦巻いている。
心拍数の上昇、顔面の紅潮、身体の硬直、思考回路及び言語中枢の混乱――前の二つはともかくも、あとの二つは深刻だ。
症状が出始めた二ヶ月前からこっち、荒事系の依頼は受けていないため、ことなきを得てきたが――
自分は、“フォア・ローゼス”の戦術司令塔なのだ。
その自分が戦闘中に行動不能となったり、判断を誤ったり、指示を伝達できなくなれば――
それは、容易に自身や仲間の死に繋がる。
(ドクトルは、大したことではないように言われていたが……)
『人なら誰しも罹る病だ。こじらせると厄介だが、お前なら大丈夫だろう』――症状の出始めに相談した際、そう言われた。
だが、こうも長引き、だんだん症状が頻繁に出るようになってきているこの現状は、立派にこじらせた状態ではないだろうか。
(本来なら自然治癒するはずの病をこじらせてしまったのか……)
自身の不甲斐無さに、レントは再び嘆息する。
このままでは、自身の命題ともいえる第一位優先事項――『ノエルを守る』という使命の遂行さえもが危ぶまれてしまう。
(今日だけで、二度もノエルと一緒にいる際に症状が出てしまっている。昨日だって――)
と、症状が出た際の自身の不手際を思い返すうち、レントは一つの事実に気がついた。
症状が出た際、必ず自身の側にノエルがいる事実に。
(……ノエルの側にいると、症状が出るのか?)
しかし、そんな馬鹿なことがあるのだろうか。特定の人物と接触した際に症状が出る病など、聞いたことがない。
特定の動物に接触すると症状の出るアレルギーはあるが、人間に対するアレルギーなど聞いたこともないし、それなら
ノエル以外の人間と接触しても、同じ症状が出るはずだ。
ならば、ノエルが身につけているものにアレルギーを誘発するような物質があるのか。しかし、自身に症状が出た時の
ノエルの服装は、旅支度だったり部屋着だったりとまちまちで、ずっと変わらず身につけているものは思い当たらない。
となると、アレルギーというわけでもない。というか、そもそもドクトルは『人なら誰しもかかる病』と言っていた。
アレルギーは一生縁がないままの人間も多いのだから、その条件には当てはまらないように思える。
(……ならば、本当に何の病だというのだろう……)
はあ、と深く嘆息し、ドクトルに改めて相談するべきかと考えた時。
「ただいま――って、レント、もう寝てるのか?」
ドアが開く音と共に聞こえた能天気な声が、やけに耳に障って響いた。
二つ取った二人部屋のうち、男二人に割り振られた部屋だ。クリスは鍛錬の一環として外へ走りこみに行っている。
一人で、誰にも気兼ねしないで済むこの状況が、今のレントにはありがたかった。
昼間はノエルの前でリンゴをぶちまけ、さっきはノエルが厨房に来た途端、何故かひどく動揺し、皿を落として割ってしまった。
幸い、自身にもノエルにも怪我はなかったし、割ってしまった皿のことも、気の好い宿の主人は笑って許してくれた。
無事だった菓子も良い出来で、甘い物好きのノエルや健啖家のエイプリルにはもちろん、自分に対して憎まれ口の多いクリス、
そして、皿の侘び代わりに振舞った店主からも、絶賛された。
だが、それでも、この気鬱は晴れない。
(このまま、この症状が続くのは拙い……)
その思いが、胸にずっと渦巻いている。
心拍数の上昇、顔面の紅潮、身体の硬直、思考回路及び言語中枢の混乱――前の二つはともかくも、あとの二つは深刻だ。
症状が出始めた二ヶ月前からこっち、荒事系の依頼は受けていないため、ことなきを得てきたが――
自分は、“フォア・ローゼス”の戦術司令塔なのだ。
その自分が戦闘中に行動不能となったり、判断を誤ったり、指示を伝達できなくなれば――
それは、容易に自身や仲間の死に繋がる。
(ドクトルは、大したことではないように言われていたが……)
『人なら誰しも罹る病だ。こじらせると厄介だが、お前なら大丈夫だろう』――症状の出始めに相談した際、そう言われた。
だが、こうも長引き、だんだん症状が頻繁に出るようになってきているこの現状は、立派にこじらせた状態ではないだろうか。
(本来なら自然治癒するはずの病をこじらせてしまったのか……)
自身の不甲斐無さに、レントは再び嘆息する。
このままでは、自身の命題ともいえる第一位優先事項――『ノエルを守る』という使命の遂行さえもが危ぶまれてしまう。
(今日だけで、二度もノエルと一緒にいる際に症状が出てしまっている。昨日だって――)
と、症状が出た際の自身の不手際を思い返すうち、レントは一つの事実に気がついた。
症状が出た際、必ず自身の側にノエルがいる事実に。
(……ノエルの側にいると、症状が出るのか?)
しかし、そんな馬鹿なことがあるのだろうか。特定の人物と接触した際に症状が出る病など、聞いたことがない。
特定の動物に接触すると症状の出るアレルギーはあるが、人間に対するアレルギーなど聞いたこともないし、それなら
ノエル以外の人間と接触しても、同じ症状が出るはずだ。
ならば、ノエルが身につけているものにアレルギーを誘発するような物質があるのか。しかし、自身に症状が出た時の
ノエルの服装は、旅支度だったり部屋着だったりとまちまちで、ずっと変わらず身につけているものは思い当たらない。
となると、アレルギーというわけでもない。というか、そもそもドクトルは『人なら誰しもかかる病』と言っていた。
アレルギーは一生縁がないままの人間も多いのだから、その条件には当てはまらないように思える。
(……ならば、本当に何の病だというのだろう……)
はあ、と深く嘆息し、ドクトルに改めて相談するべきかと考えた時。
「ただいま――って、レント、もう寝てるのか?」
ドアが開く音と共に聞こえた能天気な声が、やけに耳に障って響いた。
◇ ◆ ◇
「ただいま――って、レント、もう寝てるのか?」
走り込みから宿の部屋に戻ったクリスは、ベッドに寝ているレントの姿を見つけ、軽く目を見張った。
「……横になってはいたが、眠ってはいない。
というか、ドアをあける前にノックくらいしたらどうだ、クリス=ファーデナント」
身を起こして返してくるレントの声音は、常になくきつい。
その刺々しい物言いに、彼の毒舌に慣れているクリスもいささかむっとして、不機嫌に言い返した。
「なんで自分の部屋に戻るのに、ノックが要るんだ」
「君一人の部屋ではないのだから、当然のマナーだろう。
もしわたしが着替えている最中で、廊下に君以外の人間がいたらどうする」
レントの正論に、う、と思わずたじろいだ。しかし、ここで負けるのも癪で、苦し紛れに言い返す。
「そ、その場合は着替えの最中に部屋の鍵をかけないお前も悪い!」
「……なるほど、それもそうだな」
苦し紛れの反論でレントがあっさり納得したことに、クリスは思わず面食らう。ぱちぱちと目を瞬いた。
「……お前、今日は妙に素直じゃないか?」
「別に。正しい意見は正しいと認めるだけだ。
わたし達“ネオ・ダイナストカバル”は、神殿と違って自身を絶対の正義などだとは思っていないからな」
「……前言撤回。いつものレントだ」
さらりと神殿批判を織り交ぜてくるレントに、クリスはジト目で呻いた。
けれど、すぐにその表情を引き締め、真剣な目になると、
「けど、今日のお前はやっぱりらしくないぞ。眠るわけでもないのにベッドに横になってごろごろしてるなんて。
いつもなら、『そんな行為は時間の浪費。そんな暇があるなら魔導書の一冊も読むべきだ』とか言いそうなものなのに」
クリスの言葉に、レントは微かに眉を寄せた。彼自身、本調子でないことは自覚しているのだろう。
はあ、とレントの口から漏れた重い息に気付き、クリスは思わず眉を寄せた。
夕食後、ノエルに言われるまでは全く気付かなかったが、改めてレントの様子を見れば不調なのは一目瞭然だ。むしろ、
今まで気付けなかった自身の鈍さに舌打ちをくれてやりたいほどである。
いくら彼がポーカーフェイス――というか、単に感情の表現方法がわからないのかもしれないが――であるにしたって、
一緒にいる仲間の変調に気付けなかった自身が、無性に情けない。
本当にだるそうな様子のレントに、一度は納得した疑問が、再び鎌首をもたげた。
(――これは、本当に精神的なものなのか?)
母親が側にいないストレス――それだけで、彼がここまでになるとは思えない。それで、咄嗟に問いが口をついて出た。
「おい、ホントに大丈夫か? やっぱり、どっか具合悪いんじゃないのか?」
そんなクリスの言葉を受けたレントは、ベッドに腰掛けたまま軽く目を見張り、クリスを見上げる。
「“やっぱり”? ──わたしの不調に気付いていたのか?」
「……気付いたのは私じゃなく、ノエルだけどな」
答えながら、クリスも隣のベッドに腰掛ける。そうして、レントに向かい合う姿勢を取った。
今まで気付けなかったことへの慙愧の念から、苦い声で告げる。
「『レントさんの様子がおかしいんです』って心配してたぞ。……自覚があるなら、なんで話してくれなかったんだ」
真剣な目で、睨むように鋭くレントを見つめる。それを避けるように、レントが顔を背けた。
レントは目を逸らしたその姿勢のまま、彼らしくもなく、言い訳のような調子で言葉を紡ぐ。
「……二ヶ月前に症状が出てすぐ、ドクトルには相談した。
症状を告げたら、それは人なら誰しもかかる病で、こじらせなければ心配するようなものではないと言われて……」
だから、言うまでもないと思った。そう告げられ――クリスの胸に怒りとも悲しみともつかない感情が吹き出した。
その感情を吐き出すように、荒い怒声が口をついて飛び出す。
「症状が軽いとか重いとか、そういう問題じゃないだろう!?
何でも話してくれなんていうつもりはないが、具合が悪いときぐらいもっと周りに頼れ!
二ヶ月も黙ってて、何でもない振りして……それで、それこそこじれて手遅れになったらどうする気だ!?」
レントを真っ直ぐに睨み、一息でそう告げてから――クリスは俯き、息を深く吐いて。
一転して、静かな声で告げた。
「……一人で何でも背負い込むな。一人で……無茶しないでくれ」
あいつのように――続くその言葉は、喉の奥に押し留めて。
レントを“彼”の代わりなどと思ったことはないし、“彼”とレントを重ねて考えたこともない。
それでも、レントの姿が見当たらないと、時折ふと不安が鎌首をもたげるのだ。
“彼”のように、このまま永遠に喪われてしまうのでは――と。
そしてこの感傷は、クリスだけではなく、おそらくノエルも抱いている。おそらくは無自覚なのだろうが、言動の端々に、
この不安が表れている。
レントが単独行動を取ると、決まって酷く落ち着かなくなるのだ。今日だって、一人で支部へ顔出しに行ったレントを、
そんな必要もないのに迎えに行った。無意識に、レントが単独行動を取ることを懼(おそ)れているのだ。
“彼”のように、このままいなくなってしまわないか――と。
だからこそ、自身の不調を黙秘するレントに不安を覚えたのだ。一人で全部抱え込もうとするレントに、一人で戦い、
散って逝った“彼”の面影を見てしまって。
静かな、しかし重いクリスの言葉に、レントは逸らしていた視線をクリスに向けて、告げた。
「すまなかった……ノエルに、余計な心配をかけたくなかっただけなのだが……」
「……それが水臭いっていうんだ」
嘆息まじりで返すものの、クリスの中にもう怒りや悲しみはなく、ただただ不器用な仲間への苦笑じみた思いがあった。
その声の響きに安堵したように、硬かったレントの表情が僅かに和らぐ。
しかし、続けたクリスの言葉に、再びその表情が硬くなった。
「で――その病気っていうのは何の病気なんだ?」
「……病名は聞かされていない。ただ、心配はないと言われて……」
レントの返答に、クリスは思わず眉を寄せる。病名を伏せるというのは、あまりよくない病状の時に多い。
だが、本当にレントが深刻な状態なら、ドクトルは即刻治療体勢に入るはずだ。彼の属する組織は人員を大切にするし、
それを抜きにしても、レントの任務は組織のトップの息女の護衛だ。彼が不調となれば、彼女の護衛にも支障が出る。
そもそもレントはこの二ヶ月、ドクトルと直接会っていない。つまり、問診は携帯大首領(つうしんき)越しに行われたのだろう。
(そんな問診で、きちんとした診断が下せるものなのか?)
どうにも釈然としないドクトルの言動にクリスは顔をしかめつつも、レントに訊ねた。
「レント、具体的にどういう症状が出るんだ?」
人なら誰しもかかる病――そう称された以上、割と一般的な病なのだろう。症状を聞けば、自分にも病名がわかるかもしれない。
そう思って訊いた質問に、レントは記憶を辿るように軽く目を伏せ、症状を上げていく。
「まず一番多いのが、循環器の異常から来ると思われる顔面の紅潮と、心拍数の上昇。
酷くなると、一時的な身体の硬直や、思考・判断力の低下、言語中枢の混乱がある」
「……それのどこが大したことないんだ!?」
思った以上に深刻に聞こえる病状に、クリスは思わず声を荒げた。
しかし、病状を聞いても、全く何の病気かわからない。一つ一つの病状には病名を当て嵌められるが、それらが一度に
表れる病気など聞いたことがない。まさかそれらの合併症ということではないだろうし。
「……他に、何かないか? どんな小さなことでもいいから」
「他には――」
判断材料が欲しくて告げた言葉に、レントは一瞬何かを言いかけ――それを飲み込んだ。
「なんだ? 何かあるのか?」
「いや――関係あるとも思えないのだが……」
言葉に遠慮のない彼には珍しく、言いよどむような気配を見せるレントに、クリスは言葉を促した。
「それでもいい、気付いたことは全部言ってくれ」
逡巡するような間の後、レントはどことなく自信なさげな声音で、それを告げた。
「……症状が出るのは、決まってノエルが側にいる時だ」
「……はあ?」
余りにも予想外の言葉に、クリスは思わず目を点にした。その反応に、レントは不服そうに眉を寄せる。
「だから、関係ないといっただろう。それを君が言えというから――」
「いや……いやいやいや。待て。ちょっと待て」
クリスは不機嫌そうなレントへ片手をかざし、彼の言葉を遮った。
与えられた情報を整理するように、先程告げられた病状を、一つ一つ確認していく。
「病状は、まず顔面が紅潮する――つまり、顔が赤くなるんだな?」
「ああ」
「次に、心拍数の上昇――ようは、胸がドキドキすると」
「そういう言い方も出来るな」
「で、身体の硬直――身体が緊張して動かなくなると」
「そうだ」
「更に、思考・判断力の低下と言語中枢の混乱――頭が真っ白になって何も考えられず、うまく喋れなくなる」
「その通りだ」
「最後に、それら症状が出る時、必ずノエルが側にいる……」
「ああ――それも関係があるのか?」
頷いた後に問い返してきたレントに答える気力もなく、クリスは一気に脱力した。腰掛けていた姿勢から、引っくり返って
ベッドに倒れこむ。
その脳裏に浮かぶは、食堂でレントの不調について話したとき、一人だけ笑みさえ湛えて、「深刻になるな」と言った女。
「――こういうことか、エイプリル……」
『正解』に気付いていただろうに教えてくれなかった仲間に対し、恨みがましい声が思わず漏れた。
彼女の言う通りだ。――深刻になった分だけ、馬鹿を見た。
「……クリス=ファーデナント。わたしの病名がわかったのか?」
淡々とした中にもどこか不安げな色を宿した声で訊ねるレントにも、思わず恨みがましい視線を向けずにいられない。
どれだけ頭脳明晰だろうと、知識が豊富だろうと、情緒面では幼子に等しい彼。
だから、わからなくても――自覚できなくてもしょうがない。それはわかっている――わかってはいるが!
(これじゃあ、本気で心配して説教した私が馬鹿みたいだろうが!?)
やり場のない怒り――というか、気恥ずかしさ。それを吐き出すように、クリスは低い声を紡いだ。
「……聞きたいか?」
「――ああ」
意を決した風に頷くレントに、クリスは起き上がり、彼に向き直る。向けた視線が据わっているのが、自分でもわかった。
こんな形で自覚させることが彼にとって良いことなのか。そう制止する理性を振り切り、八つ当たりめいた感情のまま、
その言葉を紡いでしまった。
走り込みから宿の部屋に戻ったクリスは、ベッドに寝ているレントの姿を見つけ、軽く目を見張った。
「……横になってはいたが、眠ってはいない。
というか、ドアをあける前にノックくらいしたらどうだ、クリス=ファーデナント」
身を起こして返してくるレントの声音は、常になくきつい。
その刺々しい物言いに、彼の毒舌に慣れているクリスもいささかむっとして、不機嫌に言い返した。
「なんで自分の部屋に戻るのに、ノックが要るんだ」
「君一人の部屋ではないのだから、当然のマナーだろう。
もしわたしが着替えている最中で、廊下に君以外の人間がいたらどうする」
レントの正論に、う、と思わずたじろいだ。しかし、ここで負けるのも癪で、苦し紛れに言い返す。
「そ、その場合は着替えの最中に部屋の鍵をかけないお前も悪い!」
「……なるほど、それもそうだな」
苦し紛れの反論でレントがあっさり納得したことに、クリスは思わず面食らう。ぱちぱちと目を瞬いた。
「……お前、今日は妙に素直じゃないか?」
「別に。正しい意見は正しいと認めるだけだ。
わたし達“ネオ・ダイナストカバル”は、神殿と違って自身を絶対の正義などだとは思っていないからな」
「……前言撤回。いつものレントだ」
さらりと神殿批判を織り交ぜてくるレントに、クリスはジト目で呻いた。
けれど、すぐにその表情を引き締め、真剣な目になると、
「けど、今日のお前はやっぱりらしくないぞ。眠るわけでもないのにベッドに横になってごろごろしてるなんて。
いつもなら、『そんな行為は時間の浪費。そんな暇があるなら魔導書の一冊も読むべきだ』とか言いそうなものなのに」
クリスの言葉に、レントは微かに眉を寄せた。彼自身、本調子でないことは自覚しているのだろう。
はあ、とレントの口から漏れた重い息に気付き、クリスは思わず眉を寄せた。
夕食後、ノエルに言われるまでは全く気付かなかったが、改めてレントの様子を見れば不調なのは一目瞭然だ。むしろ、
今まで気付けなかった自身の鈍さに舌打ちをくれてやりたいほどである。
いくら彼がポーカーフェイス――というか、単に感情の表現方法がわからないのかもしれないが――であるにしたって、
一緒にいる仲間の変調に気付けなかった自身が、無性に情けない。
本当にだるそうな様子のレントに、一度は納得した疑問が、再び鎌首をもたげた。
(――これは、本当に精神的なものなのか?)
母親が側にいないストレス――それだけで、彼がここまでになるとは思えない。それで、咄嗟に問いが口をついて出た。
「おい、ホントに大丈夫か? やっぱり、どっか具合悪いんじゃないのか?」
そんなクリスの言葉を受けたレントは、ベッドに腰掛けたまま軽く目を見張り、クリスを見上げる。
「“やっぱり”? ──わたしの不調に気付いていたのか?」
「……気付いたのは私じゃなく、ノエルだけどな」
答えながら、クリスも隣のベッドに腰掛ける。そうして、レントに向かい合う姿勢を取った。
今まで気付けなかったことへの慙愧の念から、苦い声で告げる。
「『レントさんの様子がおかしいんです』って心配してたぞ。……自覚があるなら、なんで話してくれなかったんだ」
真剣な目で、睨むように鋭くレントを見つめる。それを避けるように、レントが顔を背けた。
レントは目を逸らしたその姿勢のまま、彼らしくもなく、言い訳のような調子で言葉を紡ぐ。
「……二ヶ月前に症状が出てすぐ、ドクトルには相談した。
症状を告げたら、それは人なら誰しもかかる病で、こじらせなければ心配するようなものではないと言われて……」
だから、言うまでもないと思った。そう告げられ――クリスの胸に怒りとも悲しみともつかない感情が吹き出した。
その感情を吐き出すように、荒い怒声が口をついて飛び出す。
「症状が軽いとか重いとか、そういう問題じゃないだろう!?
何でも話してくれなんていうつもりはないが、具合が悪いときぐらいもっと周りに頼れ!
二ヶ月も黙ってて、何でもない振りして……それで、それこそこじれて手遅れになったらどうする気だ!?」
レントを真っ直ぐに睨み、一息でそう告げてから――クリスは俯き、息を深く吐いて。
一転して、静かな声で告げた。
「……一人で何でも背負い込むな。一人で……無茶しないでくれ」
あいつのように――続くその言葉は、喉の奥に押し留めて。
レントを“彼”の代わりなどと思ったことはないし、“彼”とレントを重ねて考えたこともない。
それでも、レントの姿が見当たらないと、時折ふと不安が鎌首をもたげるのだ。
“彼”のように、このまま永遠に喪われてしまうのでは――と。
そしてこの感傷は、クリスだけではなく、おそらくノエルも抱いている。おそらくは無自覚なのだろうが、言動の端々に、
この不安が表れている。
レントが単独行動を取ると、決まって酷く落ち着かなくなるのだ。今日だって、一人で支部へ顔出しに行ったレントを、
そんな必要もないのに迎えに行った。無意識に、レントが単独行動を取ることを懼(おそ)れているのだ。
“彼”のように、このままいなくなってしまわないか――と。
だからこそ、自身の不調を黙秘するレントに不安を覚えたのだ。一人で全部抱え込もうとするレントに、一人で戦い、
散って逝った“彼”の面影を見てしまって。
静かな、しかし重いクリスの言葉に、レントは逸らしていた視線をクリスに向けて、告げた。
「すまなかった……ノエルに、余計な心配をかけたくなかっただけなのだが……」
「……それが水臭いっていうんだ」
嘆息まじりで返すものの、クリスの中にもう怒りや悲しみはなく、ただただ不器用な仲間への苦笑じみた思いがあった。
その声の響きに安堵したように、硬かったレントの表情が僅かに和らぐ。
しかし、続けたクリスの言葉に、再びその表情が硬くなった。
「で――その病気っていうのは何の病気なんだ?」
「……病名は聞かされていない。ただ、心配はないと言われて……」
レントの返答に、クリスは思わず眉を寄せる。病名を伏せるというのは、あまりよくない病状の時に多い。
だが、本当にレントが深刻な状態なら、ドクトルは即刻治療体勢に入るはずだ。彼の属する組織は人員を大切にするし、
それを抜きにしても、レントの任務は組織のトップの息女の護衛だ。彼が不調となれば、彼女の護衛にも支障が出る。
そもそもレントはこの二ヶ月、ドクトルと直接会っていない。つまり、問診は携帯大首領(つうしんき)越しに行われたのだろう。
(そんな問診で、きちんとした診断が下せるものなのか?)
どうにも釈然としないドクトルの言動にクリスは顔をしかめつつも、レントに訊ねた。
「レント、具体的にどういう症状が出るんだ?」
人なら誰しもかかる病――そう称された以上、割と一般的な病なのだろう。症状を聞けば、自分にも病名がわかるかもしれない。
そう思って訊いた質問に、レントは記憶を辿るように軽く目を伏せ、症状を上げていく。
「まず一番多いのが、循環器の異常から来ると思われる顔面の紅潮と、心拍数の上昇。
酷くなると、一時的な身体の硬直や、思考・判断力の低下、言語中枢の混乱がある」
「……それのどこが大したことないんだ!?」
思った以上に深刻に聞こえる病状に、クリスは思わず声を荒げた。
しかし、病状を聞いても、全く何の病気かわからない。一つ一つの病状には病名を当て嵌められるが、それらが一度に
表れる病気など聞いたことがない。まさかそれらの合併症ということではないだろうし。
「……他に、何かないか? どんな小さなことでもいいから」
「他には――」
判断材料が欲しくて告げた言葉に、レントは一瞬何かを言いかけ――それを飲み込んだ。
「なんだ? 何かあるのか?」
「いや――関係あるとも思えないのだが……」
言葉に遠慮のない彼には珍しく、言いよどむような気配を見せるレントに、クリスは言葉を促した。
「それでもいい、気付いたことは全部言ってくれ」
逡巡するような間の後、レントはどことなく自信なさげな声音で、それを告げた。
「……症状が出るのは、決まってノエルが側にいる時だ」
「……はあ?」
余りにも予想外の言葉に、クリスは思わず目を点にした。その反応に、レントは不服そうに眉を寄せる。
「だから、関係ないといっただろう。それを君が言えというから――」
「いや……いやいやいや。待て。ちょっと待て」
クリスは不機嫌そうなレントへ片手をかざし、彼の言葉を遮った。
与えられた情報を整理するように、先程告げられた病状を、一つ一つ確認していく。
「病状は、まず顔面が紅潮する――つまり、顔が赤くなるんだな?」
「ああ」
「次に、心拍数の上昇――ようは、胸がドキドキすると」
「そういう言い方も出来るな」
「で、身体の硬直――身体が緊張して動かなくなると」
「そうだ」
「更に、思考・判断力の低下と言語中枢の混乱――頭が真っ白になって何も考えられず、うまく喋れなくなる」
「その通りだ」
「最後に、それら症状が出る時、必ずノエルが側にいる……」
「ああ――それも関係があるのか?」
頷いた後に問い返してきたレントに答える気力もなく、クリスは一気に脱力した。腰掛けていた姿勢から、引っくり返って
ベッドに倒れこむ。
その脳裏に浮かぶは、食堂でレントの不調について話したとき、一人だけ笑みさえ湛えて、「深刻になるな」と言った女。
「――こういうことか、エイプリル……」
『正解』に気付いていただろうに教えてくれなかった仲間に対し、恨みがましい声が思わず漏れた。
彼女の言う通りだ。――深刻になった分だけ、馬鹿を見た。
「……クリス=ファーデナント。わたしの病名がわかったのか?」
淡々とした中にもどこか不安げな色を宿した声で訊ねるレントにも、思わず恨みがましい視線を向けずにいられない。
どれだけ頭脳明晰だろうと、知識が豊富だろうと、情緒面では幼子に等しい彼。
だから、わからなくても――自覚できなくてもしょうがない。それはわかっている――わかってはいるが!
(これじゃあ、本気で心配して説教した私が馬鹿みたいだろうが!?)
やり場のない怒り――というか、気恥ずかしさ。それを吐き出すように、クリスは低い声を紡いだ。
「……聞きたいか?」
「――ああ」
意を決した風に頷くレントに、クリスは起き上がり、彼に向き直る。向けた視線が据わっているのが、自分でもわかった。
こんな形で自覚させることが彼にとって良いことなのか。そう制止する理性を振り切り、八つ当たりめいた感情のまま、
その言葉を紡いでしまった。
「お前の病名は――ただの“恋患い”だ」
◇ ◆ ◇
「お前の病名は――ただの“こいわずらい”だ」
常になく据わった目で、クリスが告げた単語。
『こいわずらい』
その単語は、レントの耳に馴染みのないもので、すぐには意味が理解できなかった。病名だという以上、『わずらい』とは
『患う』の意であることはすぐに飲みこめたが――
脳内のデータベースで、その『病名』を検索する。『こいわずらい』―― 一件該当。
『患う』の意であることはすぐに飲みこめたが――
脳内のデータベースで、その『病名』を検索する。『こいわずらい』―― 一件該当。
『恋煩い/恋患い』――恋するあまりの悩みや気のふさぎ。恋の病。
「……は?」
自身の検索結果に、レントは思わず間の抜けた声を漏らす。
『恋』――その言葉の意味は流石に知っている。アルテアに読み聞かされた――というか、読むのに付き合わされた
絵本のお伽噺に、よく出てくる単語だから。
だが、その単語と、自身のことがうまく繋げられず、レントは混乱し――
その混乱から立ち直るより早く、クリスが立ち上がり、足早に部屋の出口へ――廊下への扉に向かった。
「――待て、クリス――」
思わず縋るように声をかけるが、クリスはそれを遮って、怒鳴るように一言。
「酒場にでも行ってくる!」
普段、酒など飲まないお前が何故――そう問うより早く、開けられた扉は閉じられ、彼の姿はその向こうに消えてしまった。
一人残されたレントは、言葉の意味を考える。
クリスは、自分の病気を『恋患い』だと言った。
恋とは、特定の異性に強く惹かれること、想いを寄せることだ。
(特定の異性――誰に?)
そう、自問する。
けれど、本当は考えるまでもなく答えは出ていた。
症状が出る条件――決まって、その時側にいる少女。
自身の検索結果に、レントは思わず間の抜けた声を漏らす。
『恋』――その言葉の意味は流石に知っている。アルテアに読み聞かされた――というか、読むのに付き合わされた
絵本のお伽噺に、よく出てくる単語だから。
だが、その単語と、自身のことがうまく繋げられず、レントは混乱し――
その混乱から立ち直るより早く、クリスが立ち上がり、足早に部屋の出口へ――廊下への扉に向かった。
「――待て、クリス――」
思わず縋るように声をかけるが、クリスはそれを遮って、怒鳴るように一言。
「酒場にでも行ってくる!」
普段、酒など飲まないお前が何故――そう問うより早く、開けられた扉は閉じられ、彼の姿はその向こうに消えてしまった。
一人残されたレントは、言葉の意味を考える。
クリスは、自分の病気を『恋患い』だと言った。
恋とは、特定の異性に強く惹かれること、想いを寄せることだ。
(特定の異性――誰に?)
そう、自問する。
けれど、本当は考えるまでもなく答えは出ていた。
症状が出る条件――決まって、その時側にいる少女。
(――わたしは、ノエルに……――ッ!?)
その結論に達した瞬間、
レントは頭から火を吹きそうな勢いで顔を真っ赤にし――そのくせ表情は鉄面皮のまま、思考をオーバーヒートさせて
ベッドに引っくり返った。
レントは頭から火を吹きそうな勢いで顔を真っ赤にし――そのくせ表情は鉄面皮のまま、思考をオーバーヒートさせて
ベッドに引っくり返った。
◇ ◆ ◇
翌日。
“フォア・ローゼス”の男二人は、片や慣れない深酒(やけざけ)による二日酔いで、片や謎の発熱(ちえねつ)で、それぞれ
寝込む羽目となり、大いにギルドマスターの気を揉ませることとなるのだが――
それはまた、別の話である。
“フォア・ローゼス”の男二人は、片や慣れない深酒(やけざけ)による二日酔いで、片や謎の発熱(ちえねつ)で、それぞれ
寝込む羽目となり、大いにギルドマスターの気を揉ませることとなるのだが――
それはまた、別の話である。